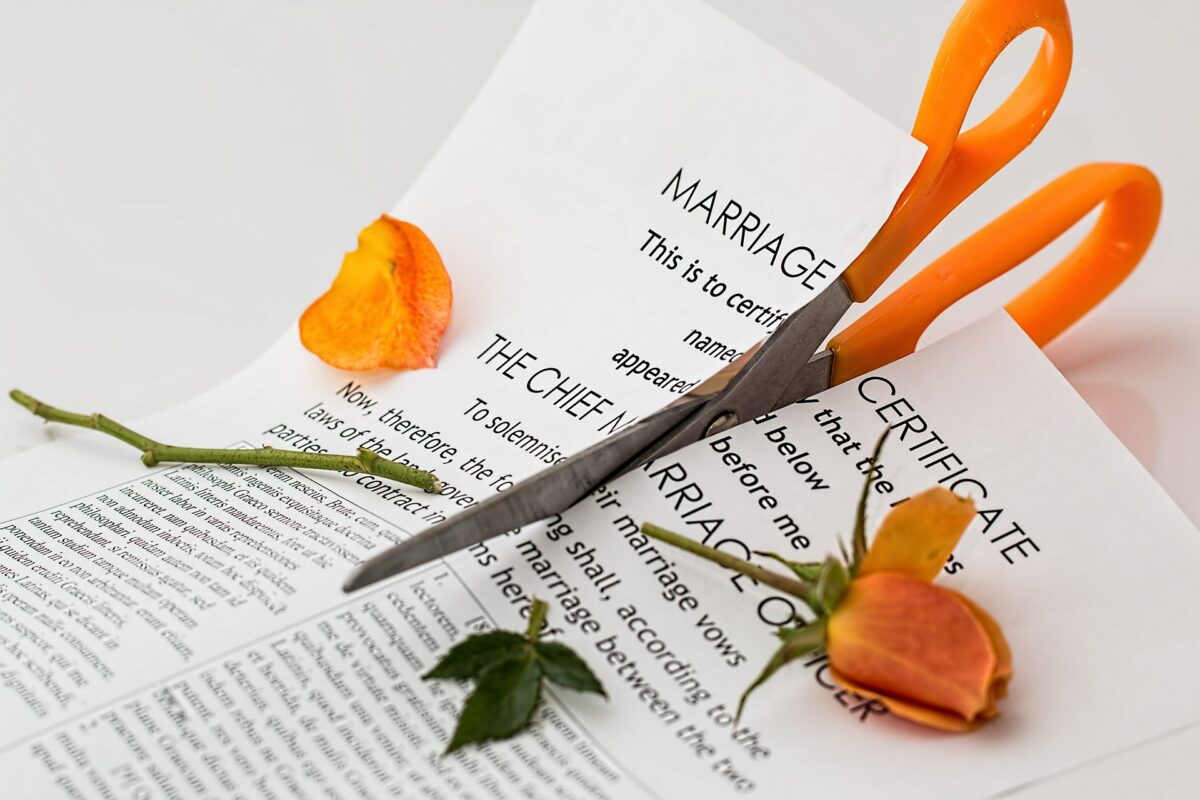離婚給付契約という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
離婚をして、夫婦がお互いに新たなスタートを切る。離婚後の人生には、きっと今までとは違った世界が広がっているはずです。
しかしながら、今後の人生における決め事を両者の間で決めておかないと、お互いにとって不幸な結果になってしまうことも。
特に、子どもがいる場合の離婚の場合は、養育費や親権等の取り決めがマストです。
今回は、「離婚給付契約」と呼ばれる契約を結ぶ場合に押さえておくべきポイントを解説します。

離婚給付契約書って?
離婚給付契約書とは、離婚における給付契約について、公正証書として公証人が作成する契約書のことです。
夫と妻の両者が離婚に合意し、これからの給付契約について定めます。
通常の契約書として作成することも可能ですが、公正証書として作成することで、金銭の支払いについて強制執行することができます。
「ないお金はとれない」というのが現実ですが、公正証書では一部強制力を有しますから、給料からの差し押さえをすることができる場合もあります。
ですので、離婚給付契約については公正証書での作成を強くお勧めいたします。
当事務所が利用する公証役場は、宇都宮公証センターになります。
離婚給付契約に盛り込むべき条項
1.離婚の合意
離婚が協議離婚である旨、そしてお互いが離婚に合意していることを記載します。
原則として、離婚給付契約書を作成するのは離婚届の提出前です。
離婚届の提出後、つまり離婚後に離婚給付契約書を作成することもできますが、双方の合意が求められる以上、締結できるとは限りません(一方の合意が取れず、公証役場に足を運ばない場合がほとんどです)。
ですので、離婚を決めた場合には、離婚届の提出前に契約書の作成を行いましょう。
2.親権者の定め
子どもについて、婚姻中は夫・妻の両者に親権がありますが、離婚後はいずれか一方の親による単独親権となります(民法819条2号)。
民法上に定められている“ルール”ですから、親権者を定めなければ離婚することができません。当然、親権者欄に記載のない離婚届は無効になります(受理されません)。
なお、兄弟がいる場合は「兄弟姉妹不分離」の考え方に基づき、全員を一人の親権者に集中させることが一般的です。特に、子供の年齢が低い場合はこの原則に則るべきとされています。
3.養育費について
「子どもが20歳に達する日の属する月まで、一か月××円の支払い義務を有することを認める」旨の条項を盛り込みます。
具体的には、
①金額
②支払期間
③支払期日
④特別な支出に関する定め(進学や入院など)
を定める必要があります。
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた現状に鑑み、今後は18歳までの支払いに着地するケースが増えていくと予想されます。
とはいえ、大学への入学に際する教育費用を考えると18歳までの支払いでは厳しさが拭えません。この点については、契約当事者の協議に委ねられます。
4.面会交流の定め
「(親権者)は、(一方の当事者)が子との面会交流することを認める/禁止する」という形で記載します。
ただし、子どもの心情や未来を考えると、完全に禁止してしまうのは望ましくありませんから、「面会交流における日時、場所、方法等の具体的な内容については、子の利益を最も優先して考慮した上で、双方の協議により決定する」といった内容を盛り込むのがよいでしょう。
5.慰謝料について
慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償の意味合いで定められます。
離婚給付についても同様で、離婚の原因となった問題に一方の責任がある場合に慰謝料の条項を盛り込むこととなります。
なお、離婚による経済的な負担を一方に強いてしまう場合に、広い意味での慰謝料が用いられる場合もあります。この点については、両者の協議に委ねられます。
慰謝料が多額になる場合、分割して支払うことが予想されます。分割の支払いにつき滞納が生じた場合、滞納額だけではなく、未払い金全額について強制執行することができるという「期限の利益喪失条項」を盛り込むことも可能です。
6.財産分与について
婚姻中に築いた共有財産(現預金、不動産など)を清算する目的で、その一部を一方から他方へ分与します。なお、慰謝料や経済的負担を考慮して、分与する財産を決定する場合もあります。
ただし、居住用不動産(自宅など)にローンが残っている場合、名義変更をするにはかなりの手間がかかります。
というのも、住宅ローンには上記で説明した「期限の利益喪失条項」が盛り込まれており、所有者が変動する場合は未払い金を全額清算しなければならない場合がほとんどだからです。
その場合は、金融機関やローン会社と協議を重ね、合意を得る必要があります。
7.年金分割について
老後に支払われる年金について、婚姻期間に応じて一部を分割請求する旨の条項です。
「対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意する」等の文言で記載します。
8.通知義務の定め
住所や職業、連絡先等の変更が生じた場合に、他方の当事者に通知をする義務を定めた条項です。
この条項の中に、通知義務を怠った場合に生じた調査費用の償還義務を定めることが望ましいです。
9.清算条項
この離婚給付契約の内容以外は、一切の権利義務を負わない旨を定めます。
離婚給付契約の要です。
10.強制執行認諾
この離婚給付契約の債務を履行しない場合に、一方が強制執行できる旨を定めます。
公正証書で定める場合でなければ、この文言が有効に働かない場合があります。
言い換えれば、公正証書をもって離婚給付契約を締結する最大の理由とも言えます。
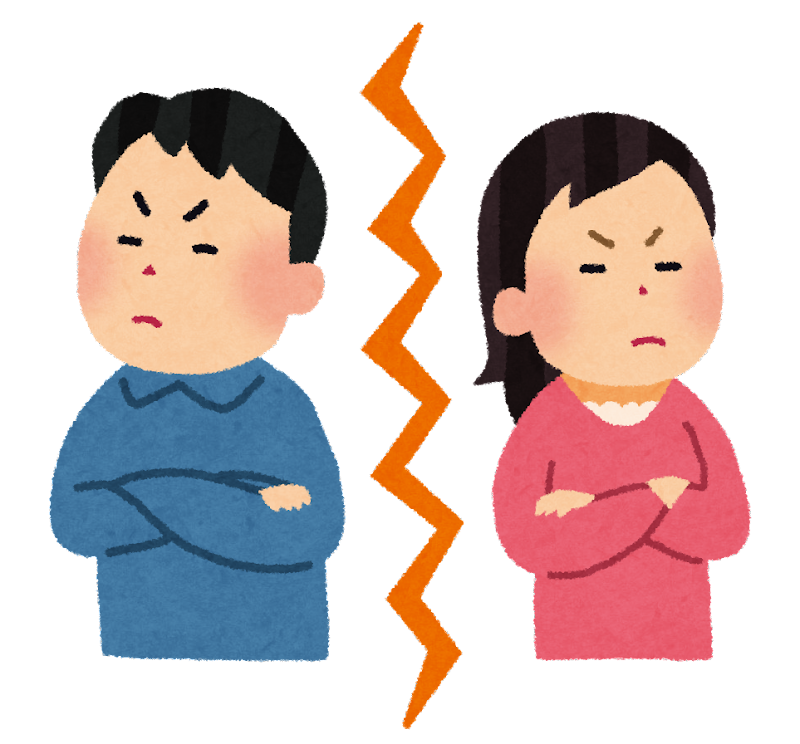
新たな人生をスタートさせるにあたって、肝心なことはしっかりと取り決めを行う必要があります。特に、金銭的な取り決めは心の余裕や安心を保つ上でも重要です。
行政書士こそね事務所は、離婚問題の相談を承っております。ご相談者様の不安や悩みが一日でも早く解決できますよう、全力でサポートさせていただきます。
お気軽に、当事務所の無料相談をご利用ください。